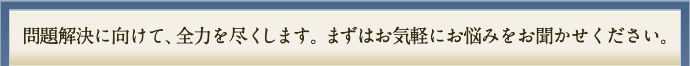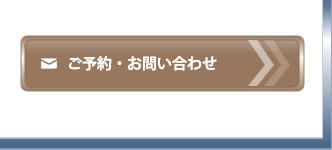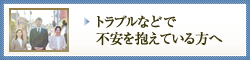相続・高齢者問題
遺言の解釈(2)【最高裁昭和58年3月18日第二小法廷判決】ポイント解説
前回に引き続き、今回は【最高裁昭和58年3月18日第二小法廷判決】のポイント解説をいたします。
ポイント①
先日、一部引用した最高裁昭和58年3月18日第二小法廷判決(判時1075号115頁)は、次のように区分することができます。
① 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究するべきである。
② 遺言書の真意を探求するにあたり、遺言書の特定の条項部分だけではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮するべきである。
この判例が先例的価値を有しているのは、②の部分になります。遺言者の真意の探求のために、遺言書外の事情(遺言書作成当時の事情、遺言者の置かれていた状況)も考慮することができることを示しました。
なお、「遺言書外の事情をどこまで考慮することができるのか」という問題は残っており、この点は次々回(遺言の解釈(4))で触れたいと思います。
ポイント②
そして、最高裁昭和58年3月18日第二小法廷判決(判時1075号115頁)では、以下を理由に、福岡高等裁判所へ破棄差戻し(再度、事件の審理を尽くすよう下級審に送り返すこと)をしています(なお、その後の経過は明らかではありません。何らかの形で和解した可能性が高いと思われます。)。
【 争点 】
かなり簡略化しますが、自筆証書遺言の条項に、「不動産を妻に遺贈する」旨の記載(①)と、「妻が亡くなった後は、子どもたちが取得する」旨の記載(②)があったため、これらの記載内容の解釈が問題になりました。
つまり、この記載の具体的に示す法律行為が何かが争点になりました。
【 判断 】
最高裁は、上記記載を文言だけで解釈してしまうと、
(1) 妻への単純遺贈。②は遺言者の希望にすぎない。
(2) 妻への負担付遺贈。②は妻に「子らへの所有権移転義務」を負担させたもの。
(3) 妻への不確定期限付遺贈、子らへの条件付遺贈。②は「妻が死亡した時点で、妻が不動産を所有していた場合には、不動産の所有権が子らへ移転する」という条件を定めたもの。
(4) 子らへの不確定期限付遺贈。妻は不動産の処分を禁止されており、使用収益権を有するのみ。
と、四通りの解釈ができてしまう(遺言の文言だけでは遺言者の真意がわからない)ので、福岡高等裁判所の遺言解釈方法に誤りがあるとしました。
以上のとおり、複数の遺贈の類型を記載しましたので、次回は、遺贈について紹介したいと思います。
武雄オフィス所長 弁護士 矢野 雄基
参考文献: 遺言と遺留分 第1巻 遺言 P305~P341、P355~P377